31. 新版 広辞林
32. 新版 広辞林=2=
33*. 日本大事典 言泉
34*. 岩波 日本古典文学大辞典
35*. 西郷信綱 日本古代文学史
36. 基本古語辞典
37. 定家明月記私抄
38*. 谷崎潤一郎訳源氏物語 全 (新々訳)
39. 新版 眠れない話
40. 全訳 漢辞海
ページ先頭のタイトル・リストで、番号に"*"を付けた項目は、対象となる本は手持ちではなく、図書館等で読んだものであることを示す。
31. 新版 広辞林
三省堂
金沢庄三郎編 三省堂編集所修訂
新版廣辞林の序
(「辞」は旧字体だが、指定の仕方がわからなかったので新字体にした。以下、多くの旧字体は新字体で代用している。)
・・・・
廣辞林を発刊してより實に三十有数年の歳月を閲し・・・・
旧来の国語辞典も、これらの新情勢に対して何らかの修訂を迫られる段階に立ち至ったのである。
・・・・
版元書肆より、その長を伸ばしその短を削って時勢に即応したものにしたいとの懇請頻りなるものがあり、編者もその趣旨を諒とし、ここに新版廣辞林の上梓を見たのであるが、當用漢字、新かなづかひに就いては賛意を表し難いものがある。
この辞書は、私が中学生のころに買ったものと思う。
ちなみに、私が持っている新版16版の発行は、奥付によれば昭和38年9月10日で、その時は私が13歳の中学1年生になる。また、新版は昭和33年3月5日である。
この辞書は最初はよく使ったが、もう使わなくなって30年以上になるだろう。内容がだいぶ古びている。
なぜ今まで処分しなかったかというと、「前書き・後書き」とは関係ない。
この辞書の最後に収録された単語は、「んとす」であり、その例文が「広辞林の修訂まさに成ら―」となっている。
この辞書の収録項目は「あとがき」によれば、「およそ十三万六千項目に及んでいる」のであり、そのまさに最後の項目で「広辞林の修訂まさに成ら―」というのが出てくるのだ。
この辞書の本文は、「広辞林の修訂まさに成ら―」で終わっているのである。
辞書の編集作業は困難を極めるものと思っている。その困難な作業の末に、「まさに成らんとす」と、編集者の真情を吐露しているように思えるのだ。
さらに、この例文を採用するに当たっては編集者の間で議論があったのではないだろうか、と想像をたくましくしてしまう。
「この例文はあまりに手前みそではないですか」、「いや、この最後の収録語の例文としては実にぴったりでしょう」、などという議論をつい想像してしまうのである。
2000ページを超えるこの辞書を、今後も実用としては使うことがないことを確信しているにもかかわらず、単に捨てられない理由は、実にこの最後の単語の例文にある。
脱線がが長くなったが、今回、改めてこの「序」を読んでみて、「當用漢字、新かなづかひに就いては賛意を表し難い」というところにひきつけれた。「當」であり、「かなづかひ」である。
よく読んでみると、この辞書では、まず編者金澤庄三郎氏による「新版廣辞林の序」があり、続いて、三省堂編集所による「序にそえて」がある。
「序にそえて」では、「ただ最近の国語教育界の動向をかんがえ、当用漢字、新かなづかい、その他新しい表記の方法を採用したが、これは、まったく編集所の責任であって、先生の御意志ではない」とある。
国語の表記の改革は戦後間もなく始まり、幾多の改革が行われた。
改革がスムーズに進んだものではないことは承知しているが、ここに生々しい実例の一端がうかがえる。
当用漢字字体表は1949年(昭和24年)4月28日に告示された、とWikipediaにある。逡巡と混乱は、9年後の昭和33年になっても終息していないのである。
編者の金澤庄三郎氏と三省堂編集所との間で、どのような議論がなされたのであろうか。知りたいと思っても今となってはかなわないだろう。
巻末には同じ三省堂編集所による「あとがき」がある。「新版廣辞林の序」、「序にそえて」、「あとがき」の三つを読み比べると非常に興味深いものがある。それについては次項にゆずる。
【注】雲に関する解説書を昔読んだことがあり、その中で、作家の新田次郎氏が、当用漢字音訓表の発行の影響により、気象庁内で「巻雲」から「絹雲」に表記を変えたエビソードがある。私の記憶では次のような内容だった。
当用漢字音訓表が文部省から発行された。「巻」については「まき、かん」という書籍などの巻号を呼ぶ読みだけが登録され、「けん」という読みは除外されていた。
気象庁は文部省の管轄であり、それに従わざるを得ないという空気であり、「巻雲」を今後は「絹雲」と書く、という通達が回された。
通達は全課長が押印して承認となるが、測器課長の新田氏は「巻雲」が正しいのだから変えるのは認められない、という考えで、届いた通達は印を押さずに机の上に未処理の書類として放置していた。
回覧はストップし承認にならない。
ある時、新田氏は大阪への出張を命ぜられた。
大阪の出張先に着いてみると大した用事がなく、どうして出張する必要があったのだろうか、と不思議だった。
出張から帰って机を見ると、印を押さずに残してあったはずの通達の回覧文書がない。
課長代理に聞くと、「それはとくに問題なさそうなので代理で処置しておきました」との答え。
このときに「図られた」と気付いた。
記憶がちょっとあいまいなので、こちらを参照させていただいた。その情報によると、現在はまた「巻雲」という表記に戻っているようだ。
32. 新版 広辞林=2=
三省堂
金沢庄三郎編 三省堂編集所修訂
「序」、「序にそえて」、「あとがき」について
文章ではあらわせないことなので、画像データを示す。(横線は筆者(当サイト管理人による)
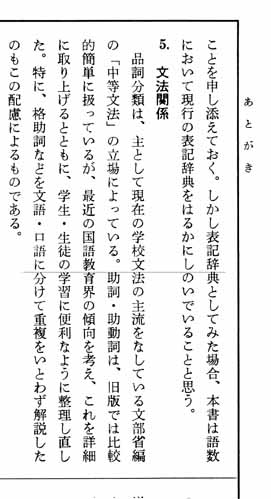
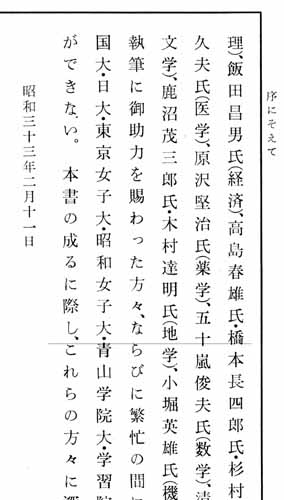
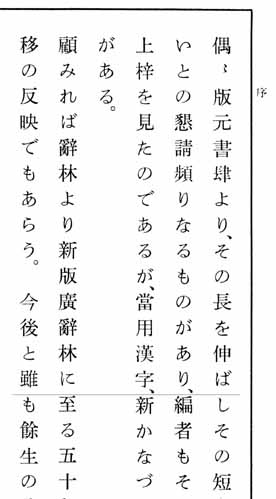
まず気がつくのは、句読点の扱い方の違いである。
「序」では、句点、読点ともに文字間のスペースに配置され、読点の次の文字は密着しているが、句点の次は1文字空白を入れる。
「序にそえて」では、句点、読点ともに文字間のスペースに配置されることは「序」と同じだ。
こちらにはさらに中黒(「・」)、カッコ(「()」)が多数使われているが、最後の2行を見るとどちらも文字間のスペースに配置されていることが分かる。
ただし、カッコと読点が続くと文字間のスペースには入りきらないので、すこし後ろにはみだし、そのずれはその後の文字のずれを引き起こす。
中央の画像に横線を引いたが、文字がずれて、横方向の文字位置が波打っているのがわかる。
「序」にはカッコも中黒も使われていないので、比較できないが、基本的に同じ構造のようだ。
したがって、「序」と「序にそえて」は、旧字体・旧かな遣いと新字体・新かな遣いの違いのようだ。
「あとがき」では、新字体・新かな遣いであるほか、句点・読点のほかに、中黒、カギかっこまで一文字のサイズとなり、現在の方法と同じである。
画像には含まれていないが、別の場所ではカッコが使われており、"(「"とか"」)"もある。
記号が単独で(連続しないという意味)使われる場合は、カッコは文字間のスペースに埋め込まれ、カギかっこは通常の文字と同じ長さが確保されている。
これが2種類が続くとき、たとえば"」)"のような場合は微妙な長さになる。
明らかに1文字より長く2文字よりは短い。
1文字のサイズに押しこめると狭すぎ、2文字分をとると間隔が空きすぎてしまりがなくなる、という印象は確かにある。
整数文字の長さにならないとすると、そのあとに続く文字の位置もずれていく。
行のおしまいは整列させないと美しくないので、どこかで文字間隔を調整することになる。
記号が単独で使われる場合は一文字分の長さ、二種類の記号が連続したときには一文字を超え二文字を超えない長さになる、という現象が広くあてはまることは、他の本を当たってみるとすぐにわかる。
例外は新聞で、私が購読している朝日新聞では、二種類の記号が連続した時もそれぞれが一文字分のサイズをとる。
「しまりがない」という印象が少ないのは一行の文字数が12文字と少ないからだろう。
また、中途半端な長さにすると、一行の文字数が少ないので調整する余地が少ないということにもなる。
一番気になったことはこれではない。
「序」、「序にそえて」、「あとがき」と三つ並べると、統一性が感じられないのだ。
かな遣い、字体は、それぞれについて、旧・新・新、となるが、句読点の文字サイズは、0・0・1になる。
つまり、「序にそえて」が中途半端なのだ。
句読点の文字サイズは、本文からあとがきまで"1"文字確保する方式でありながら、「序にそえて」では「文字間のスペースに押し込める」ことにしたのは、序文のような文章にはこれがよい、と判断したのだろうか。
あるいは、「序」と同じ表記にしたかったが、本文を「当用漢字、新かなづかい」の路線に切り替えることにしたので、「序にそえて」でもそうせざるを得ず、そこで句読点の文字サイズについては今までと同じにした、ということだろうか。
句読点は日本人の発明である。当然、簡単にはできない。
平安時代には、かな文字による文学でも句読点は一切ない。手元に「和泉式部日記」の印影本があるが、本当に句読点が全くなく、漢字と仮名文字がだらだらと続いている。
ただし、和歌が挿入されるときには改行が行われる。
江戸時代はどうなんだろうかと思って探したところ、上田秋成の「雨月物語」の影印本(*1)が東京大学からネットで公開されていた。
翻刻されたテキストは、たとえば、古典文学ガイド-近世-雨月物語 (*2)にある。
翻刻されたテキストの冒頭は(A)であり、影印本の書き方に忠実に修正したものは(B)になる。
影印本の理解は私の想像の範囲を出ないので、信頼性に不安はあるが、点の位置についての間違いはないと思う。
(A) あふ坂の関守にゆるされてより、秋こし山の黄葉(もみぢ)見過しがたく、浜千鳥の跡ふみつくる鳴海がた、不尽(ふじ)の高嶺の煙、浮島がはら、清見が関、大磯小いその浦々。
(B) あふ坂の関守にゆるされてより。秋こし山の黄葉(もみぢ)見過しがたく。浜千鳥の跡ふみつくる鳴海がた。不尽(ふじ)の高嶺の煙。浮島がはら。清見が関。大磯小いその浦々。
現代文で「、」、「。」とするところを全部「。」をつかっている。つまり、「、」の表現はない。
最初の一文だけを見ただけだが、句点・読点に当たるものがすべて"小さな丸"で表現されている。
つまり、「句点・読点を区別せずに同じマークを付けている」のである。
とにかく、これは大きな前進といえる。
江戸時代は書物が大衆化した。
落語に、読み本を"立て板に水"だ、と言いながら、つっかえつっかえ、しかも間違えて読むという「浮世床」がある。
それほど大衆化したので、少しでも読みやすくなるように工夫がなされたのだろうか。
33. 日本大事典 言泉
初版は大倉書店発行
落合直文、補遺版には森林太郎の序あり、改修版では芳賀矢一改修
「序」
[文末]
今や本書を刊行するまでに運んだのは、編集員諸君の勉強にも因るが、労銀や紙価の暴騰を物ともせず、一意此の事業に熱誠をこめた書肆の労苦も、亦大いに多としなければならぬ。
「序」
[文末]
森林太郎しるす
「緒言」
[文末]
辞書編集は、余の早くよりの志なり。明治廿一年のころ、有志者あつまりて、言語取調所を起ししが、余も、その設立者の一人となり、よろこびて、それに従事せしに、いくばくもなくして、かの取調所は帝国大学の方にうつされたり。されど、余は、余の志をつらむかむとて、常に言語の採集を怠らざりしが、明治廿七年の秋には、その草稿、三十余巻になれり。
....
[文末]
この辞書、編集員をあつめて従事することになしたるは、実に廿七年の九月一日のことなりけり。午前は、解釈に従事し、午後は、言語の採集に従事せり。その採集は、新聞雑誌をよむもの、謡曲戯曲をよむもの、小説をよむもと、軍記をよむもの、俳書をよむものなど、各、その分担を定めて従事せり。
私が目にしたものには、「序」に相当するものが三つ並んである。
日付を見ると、新しいものから順に並んでいる。したがって、三番目の「緒言」が最初のものである。
明治24年に編集所を設立して辞書編集を始めたようだ。
この年はどんな年かとおもい、コンサイス世界年表(*3)をあたってみた。
すると、3月31日に、帝国大学の臨時編年資料編纂掛と地誌編纂掛を合併し史誌編纂掛に改組、とある。
この動きと連動したものだろうか。そうでなくても、このころは、学問の世界の組織編成は盛んにおこなわれていたのであろう。
「三十余巻」になった草稿をもとに、明治27年9月1日に編集員を集めて体制を作って辞書編集の具体的な作業にかかった、とある。
そして明治29年の秋には編集がほぼ終わり、出版の広告を出すが、そのころに帝國大辞典、日本大辞典などが相次いで出版され、競争するような状態になりそうだとの懸念から延期した、とある。
この延期が意外な問題を引き起こす。
明治27年8月1日、清に宣戦布告して日清戦争が始まる。翌28年には講和に至り、日本が台湾を領有することになる。
この日清戦争が辞書の編集に影響したことが書かれている。兵站部、戦利品、もりそんざん(原文のまま)、新高山などが新語として採択される必要にいたり、そして「日本」という言葉の解釈までも書き換えが必要になった。
この辞書はいわゆる百科語を含むものだから、地名にしても説明が必要になる。
百科語を含む辞典にすると、いろいろと問題が出てくるということがよくわかる。
私が以前に感じたことに、たとえば市の名前を引くと人口の数字が出ていることがあり、時にはいつの統計による数字かということで、「年」の表記を見ることもある。
それを見ると、こんなに古い値なのか、と驚くことが多い。
「年」の表記がなくても自分の住む市を引いてみた数値はかなり古いことが分かることが多い。
問題なのは、どのくらい古い数値なのかがわかってしまうことだろう。固有名詞を除けば、古い、新しいの区別はさほど目立たない。もっとも最近では、IT関係の言葉がどれくらい採録されているか、ということである程度は見当がつく。
二番目の「序」については略すが、これを書いた森林太郎というのは、森鴎外だろうか。この点が気になる。
最も新しい「序」だが、その末尾は、「労銀や紙価の暴騰を物ともせず、一意此の事業に熱誠をこめた書肆の労苦」とある。
編集者サイドの代表が出版社にたいして謝辞を述べる、というのは珍しいのではないだろうか。
この「序」の日付は大正10年11月である。ここでもコンサイス世界年表を引く。
前年の大正9年には、4月に「商品相場暴落」とある。前後して、労働組合の結成とストライキ、企業の倒産、原首相の暗殺、ワシントン会議で日本艦船の制限の決定などの項目が並ぶ。
もう少し調べてみると、大正3年に第一次世界大戦が勃発、以後日本は特需景気に沸いた。
この年、日本日英同盟のよしみでドイツに宣戦布告し、間もなく日本海軍は赤道以北のドイツ領南洋諸島を占領、大正7年には第一次世界大戦が終戦を迎えたが、戦後も間もないときまでは特需景気で日本は潤うが、すぐにその反動で大正9年の恐慌となる。
日本史の高校生向け参考書(*4)でチェックすると、「1920年3月にはじまった戦後恐慌が日本経済を空前の繁栄状態からいっきょに不況のどん底につき落した」とある。
戦後とはここでは第一次世界大戦であり、1920年は大正9年である。
この2年前から米騒動が全国にひろがった、とか、小作争議が1921年(大正10年)から急増した、など、日本中が騒然としていた状態にあったようだ。
なるほど、この恐慌のさなかに増訂版が発行されたのか。このような社会情勢によって、あのような序文が生まれたのだ。「労銀や紙価の暴騰」であり、「書肆の労苦」とわざわざ書くことになったのだ。
もともと、この本の序文を読んだのは、上に書いた「広辞林」の序における句読点などの書き方(現実には印刷の仕方)を調べようと思ったからだった。
ここで、序文の書き方について見てみることにする。
明治31年の最初の「緒言」では、句点・読点共に字間に配置し、句点の次に1字分の空白を置くことはない。
その次の明示41年9月の「序」では、句点・読点共に字間に配置するのは同じで、句点の次に1文字の空白を挟むことが起こっている。
もっとも新しい大正10年11月の「序」では、句点・読点共に字間に配置するのは同じである。
句点の次の空白については、混乱している。句点ごとに、空白ありは○、空白なしは×と表記すると、順に"×○○○○○×○○"となる。
なお、句点の次で改行している場合には空白の有無はわからないので除いてある。
○が多いので、「基本は○である」と仮定すると、×については、たとえば行の終わりがちょうど切れ目のよい位置になるように空白文字を省略した、という可能性が考えられる。
しかし、最初の×の行は、「明治四十一年」というところの「明治四」のところで次の行に移っており、その可能性はない。
ついでに「凡例」を見ると、「序」に比べて少し小ぶりの活字だが、句点・読点共に字間に配置し、句点の次に空白文字を置かない、という原則が完全に守られているようだ。
もっとも、全文を見たわけではなく、ざっと眺めた程度ではある。
これは、最も古い「序」と同じである。
凡例は最も新しく書かれたものであろうから、その書き方が、序文の中でもっとも古いものと一致する、というのは不思議なことである。
さて、本文(単語の説明している文)はさらに小さなサイズの活字だが、ここでは、句点・読点共に1文字の7, 8割くらいの大きさのスペースを確保している。
句点に続く空白文字はない。この本文は文字サイズが小さいから、句点・読点を文字間に追いやるのは無理であり、この措置は妥当だろう。
34. 岩波 日本古典文学大事典
岩波書店
市古貞次 野間光辰
序
[文頭]
『日本古典文学大辞典』全六巻、ようやく成る。
....
[文末]
企画立案の当初より適切な助言を惜しまれなかった佑田善雄氏を早く喪い、さらに編集委員として終始重要な役割を分担協力せられた大久保正氏の急逝に遭ったことは、なんとしても悔まれてならぬ。そのほか本辞典への寄稿が絶筆となった方々も十指に余る。もし霊あらば来って我々と刊行の喜びを共にし、所期の如く本辞典が日本古典文学の研究と鑑賞に貢献することを温く看守り給えと祈る。
『日本古典文学大事典』全六巻、ようやく成る。
最初にこの序文を目にしたとき、「おおおっ」と声を上げそうになった。
はじめにズバッと結論を言う。すがすがしい。ある詩を連想した。
高村光太郎 「冬が来た」(*5)
きつぱりと冬が来た
八つ手の白い花も消え
公孫樹(いちょう)の木も箒(ほうき)になった
....
詩の一行目の「きっぱりと冬が来た」という簡潔な表現で、冬の寒さがリアルに迫ってくる。無駄をそぎ落として本当に必要なことだけをいうのは強い。
「ようやく」という言葉に編集作業の苦労がにじみ出ている。
その後、本書の目標や企画、編集の経緯などが述べられて結辞に至る。編集の過程で重要な役割を果たした二人が刊行を目にする前になくなったこと、そして、この辞典への寄稿が絶筆となった方に言及する。
たしかに、完成前になくなってしまう、というようなこともあるのだろう。
特に辞書、辞典、事典などの編集には経験豊かな人物が編集者となるのだろうから、そういうケースもあるのだろう。
この文章を読むと、編集グループの心温かな人間関係を自然に想像してしまう。
黙々と原稿の編集に打ち込み、あるいは内容について熱い議論を交わし、そして一段落したら熱いお茶をすすりながらつれづれの話題に花を咲かせている、という編集室の様子を想像してしまうのだ。
想像するのは私の自由ですから。
35. 西郷信綱 日本古代文学史
岩波現代文庫
岩波書店
西郷信綱
岩波全書改稿版はしがき
[冒頭]
この「改稿版」は、旧著に手を入れたいわゆる修正版ではなく、新規に書きかえたものである。そして当然ここに旧著は放棄される。それも、勉強したところほど変貌し、怠けた部分がいささか旧態をとどめる仕儀になった。今後、勉強をせいぜい自分に課するほかはない
....
改訂版に対する前書きが書かれることはよくある。
特に辞書は改訂することが必須であり、改訂ごとの前書きが巻頭に並んでいることが多い。
改訂版に対する前書きの多くは、新たに何が追加されたか、を書き、また削除したことについても書かれることは多い。
しかし、このように、旧版と(あまり)変わっていないことについて書くことはめったにないのではないだろうか。
変わりがない、という場合、変える必要がないから変えなかった、という場合と、変えるべき(かもしれないも含む)だが、何かの事情で変えることをしなかった、という場合の二つがある。
前者の「変える必要がない」という場合は何も問題はない。
後者については、「変えるべき」ということがはっきりわかっていて変えなかったという場合もあるだろうし、それがはっきりしていないという場合もあるだろう。
本書では、変えるべきところを変えたところで、全体を読み返したのだろうか。
「ここは手つかずか。勉強しなかったからなあ。」
「気になることはあるのだが、その前にやるべきことがいろいろあるからなあ」
などのひとり言を想像してしまう。
「怠けた」という言葉に、「気になりながらも手がつけられなかった」という状況があったのだろう。
ひとつひっかかることがある。
これは「改稿版」であり、「修正版」ではない、と書かれている。そのあとに、「旧著は放棄される」ともある。
修正版であるなら、必要な修正をおこなったのだがら、修正すべき内容が含まれている旧版は破棄されるのが当然である。
しかし、「新規に書きかえた」のなら、それは「独立したもうひとつの作品」であり、旧版と並び立つものではないだろうか。
そう考えると、「旧著は放棄される」というのが、いまひとつ納得できない。
おそらく、「修正版」のイメージが、細かいところをあちこちと修正した、というものなので、今回は全面的に書き直したのだから、「修正版」と呼ぶレベルではない、ということなのだろう。
書き直しているときに、ある部分は気になることがないわけではないのだが、それについて新しいことがわかったということもないので、とりあえず元の文章のままにしよう、ということだろう。
旧版と同じ内容とはいえ、とにかく、今回書いたのはたしかだ、ということである。
おもうに、著者は、ある部分について、すこし詳しく検討してみたいが、今の時点でその余裕がない、と、悔しい思いをしながら、元の文章と同じ内容をもう一度書いたのだろう。
それが、冒頭の「改稿版」という言葉にこだわった理由なのだろう。
「怠けた」という言葉の裏に「悔しい思い」がこめられているような気がしてきた。
またしても、勝手な想像です。
36. 小西甚一著 新装版 基本古語辞典
大修館書店
小西甚一
著者のことば
はじめに
....
そんなことを考えたり話したりしているうち、自分がそれを実行しなくてはならない事態となり、この辞典が生まれた。着手したのは昭和三七年五月だから、あしかけ四年になる。
その間、悪戦苦闘の連続だった。なぜそんなに苦労したかというと、すべてを根本からやり直したからである。参考のため、いくつかの古語辞典を調べてみたが、驚いたことに、語釈・用例ともに大部分は先行辞書のまる移しというものが多い。・・・・
さすがに良心的だなと感心させられた古語辞典が、ひとつだけ存在する。わたくしは、その辞典に高い敬意をはらい、用例はすべてそれと違ったものをあげ、(ほかに用例がない語は別として)、語釈も新しい言い回しで押しとおした。
本題に入る前にどうしてもひとこと触れないことができないことがある。
小西甚一著
「著」である。「編」ではない。まして「監修」ではない。小西氏が一人で著したのである。
辞書の編著者としては、多くの場合、最初に「"大"先生」の名前があり、次に「"中"先生(大体はその弟子筋)」の名前が来る、ということが多い。
「大先生」は、あの世に行ってしまった名前が引き続いて使われていることもよくある。
では、どのような影響を受けているのか。辞書の編集方針を踏襲している、ということだろうか。
また、「中先生」は、その弟子筋、もう少し丁寧に言えば、大先生の学恩を直接的に受けた先生であることが多い。これは、前書きなどを読むとわかる。
辞書で、「著」と書かれたものは、私は持っていない。
ネットで見ると、「新版 大言海」が「大槻文彦著」と見える。このような、パイオニア的な辞書でないと無理だろうと思う。
ここで、まえがき(「はじめに」)に戻る。
「先行辞書のまる移し」というのはよく聞くことである。
「すべてを根本からやり直した」のなら、苦労するのは当然で、「悪戦苦闘の連続だった」のは言わずもがなである。
「あしかけ四年」とは、採録語数を厳選したことにより4年ですんだ、というべきだろう。長いわけではない。
「感心させられた古語辞典が、ひとつだけ存在する」
これって何だろう。
「語釈・用例ともに大部分は先行辞書のまる移し」でないのだから、語釈・用例がユニークなものである。
ユニークと言えば、岩波古語辞典がある。
見出しが、活用する語については、終止形でなく連用形である。
おぼろげな記憶では、私が高校生の時に教師から、この辞書は動詞、形容詞などが終止形ではないので注意するように、と言われたような気がする。
もっとも、注意するように、ではなく、使わない方がよい、というようなことだったかもしれない。
なにしろ、45年も昔のことなので、記憶はあいまいである。
巷では、終止形で載せていないからこの辞書は使ってはいけない、といわれた、というようなケースもあったように思う。
この辞書の前書き・後書きについてはすでに取り上げている。
用例について、とても気に入ったものがあるのだが、前回は書かなかったので、ここで書いておく。
岩波古語辞典 「ありあけ」
(2)『「有明かし」に同じ(注:有明けまでともしておく燈火、または行燈(あんどん)とある)。』、として、用例がある。
「夜詰め已後、有明けの他、燈(ともしび)立て置く事、過料銀二枚」<上杉家文書三、元和八・一一・一五>
已とあるが、巳(み)の刻ではないだろうか。
巳、已、己の3文字は昔から混同されることがあったようだ。時間があれば、上杉家文書に当たってみたい。
巳の刻は、朝の10時前後の2時間とされるので、9時~11時。
従って、有明け以外の明りを朝9時以後までつけておいたときには、罰として銀貨2枚をとられる。
「昨日はそれがし、読み書きしておって、朝になって、明りを消すのを忘れて銀二枚を召し上げられた」
「それは難儀なことであった。明日は気をつけねばならぬのう」
これは、言葉遣いとしてはいい加減だが、このような雰囲気だろうか。
「有明けの他」という部分はよくわからない。
有明け行灯は昼間でも点けておくものなのだろうか。
小西甚一著の基本古語辞典に戻れば、「有明け行灯」の義に対する用例は、以下である。
「今のは何ぢゃ。女子(をなご)ども、有明けの火も消えた」[近松・曾根崎]
夜に、何かの音で目を覚ましたとき、有明け行灯の火が消えていて、大店の主人か番頭が声をあげている様子を想像した。
ネットで、曽根崎心中のテキストを探した。
http://homepage2.nifty.com/hachisuke/yukahon/sonezaki.html
この辺りのテキストを抜き出すと、以下である。(改行は読みやすいように付け加えてある)(*6)
亭主奥にて目を覚まし。「いまのはなんぢゃ女子ども。
有明の火も消えた。起きてともせ」と起されて、
下女は眠そに目をすり/\しどけなりふり起出て、
「旦那さんなんぞ用かいの」
「なにやら大きな音がした。行燈の火をともしてみい」
「ほんに、こりゃ真暗がり、火打箱はどこぢゃやら」と探り歩くを
このようなところを見ると、有明け行灯とは、今の常夜灯のようなもので、通常は夜通し付けておくものだということがよくわかる。
この辞書はとてもよい辞書である。
それは確かだが、収録語数が少ないという点は最初から頭に入れておいた方がいいだろう。
たとえば、盥(たらひ)、半挿(はんざう)は、最近、私が「落窪物語」を読んでいて辞書を引いた単語だが、収録されていなかった。
他の多くの高校生用古語辞典には採録されている。
確かに、「源氏物語」では少なく、盥は1か所、半挿はなし。
一方、「落窪物語」には、「盥、半挿」または「半挿、盥」と続く形で、合計4回出てくる。
ちなみに、上で触れた岩波書店の古語辞典では、盥の用例は、この「源氏物語」の唯一の個所を採録している。
37. 定家明月記私抄
ちくま文芸文庫
筑摩書房
堀田善衛
序の記
....
戦時中のある時期にこの三巻本を手にして、私はほとんど呆然としてしまったものであった。漢文体であることは言うまでもなく、それもむずかしい漢字ばかりが詰め込まれていて、返り点も何もなく、読み下すだけでさえが難儀な、一種独特の文章が上下二段に黒々と組み込まれているものを、ただ要するにためつすがめつ眺めて暮すほどのことしか出来なかった。
....
長い時間をかけて、本当にぼつぼつという感じで、あるときには一年に一度もひらくことなしに、またときには、その時々の自分の年齢と同じい時に、定家氏が何をしていたかを見るためにひらいてみるというようにして馴染んで来たものであった。
....
もとより私はこの漢文書き下しの、癖の多い文章を、いまにしても自由に読みこなせているわけではないので、読み違えたり、とんでもない解をつけたりもするかもしれない。今川文雄氏の『訓読明月記』(河出書房新社)が刊行されなかったならば、私にしてもこのようなものを書き出そうとはしなかったであろう。また、石田吉貞氏、安田章生氏、村山修一氏、辻彦三郎氏などの浩瀚な研究によることも多大であることも言を待たない。
....
小説家でも、「読み下すだけでも難かしい」本らしい。
ためつすがめつ眺めて暮す、とある。
手にとってパラパラとめくり、漢字をちょっと眺め、ばたんと閉じて机の上に置き、
またある時、ふと思い出し、机の上のこの本を手に取り、自分の年齢に相当するページを開いて、漢字を眺め、読み方を想像して意味を考え、
また、ばたんと閉じて机の上に置く。
こんなことをしていったのだろうか
ためつすがめつ、だから、読むのではなく眺める、ということなのだろう。
本書の後記にはこうある。
「戦時中からの四十数年間、私はぼつぼつとこの幻と付き合ってきた。ここに、定家十九歳から四十八歳までの記の私抄を世に送る。」
日付は「一九八六年」とある。
40年にもわたって、読み、理解しようと努め、ようやく考えがまとまり、書くことができた、というのである。
本というものは、これほど勉強しないと書けない事がある、ということか。
明月記は、大まかに言うと、今から800年くらい昔に書かれた日記である。
では、現在書かれている作品で、800年後に伝わる作品はあるのだろうか。
800年後に、人生の半分を費やして、読みとろうとしてくれる人が出てくるような本はあるだろうか。
確かなことは、全く予想がつかないということである。
38*. 谷崎潤一郎訳源氏物語 全 (新々訳)
中央公論社
谷崎潤一郎
新々訳源氏物語序
・・・・
・・・・今度の新々訳は三回目の翻訳である。・・・・
中央公論社が「日本の文学」の第一回として私の作品集を出版するに当り、枉(ま)げて仮名遣いを新仮名にすることを承諾してくれと言われて、ついに私は節を屈することになった。それが今回源氏の新々訳を思い立つに至った事の起りである。
・・・・古くは与謝野夫人の訳を始めとして、今日では源氏物語の現代語訳は数種類ある。いまさら新々訳でもあるまいと言われそうだが、翻訳者の身になってみればそうでもない。私以外の翻訳者の訳文は皆新仮名遣いになっているのに、私のものだけが旧約も新訳も旧仮名になっている。すでにわたしの創作集の一部が、「日本の文学」の一冊として新仮名に改められて発行され、やがてはその続刊も発行されようとしているのに、谷崎源氏が依然として旧態を墨守し、そのために若い読者から疎(うと)んぜられているとすれば、翻訳者の私はやはり寂しい。私とすれば一人でも多くの人に谷崎源氏を読んでもらいたいのが本心である。それでなければせっかくの仕事の意義がない。
・・・・旧訳の序で述べた通り、「これは源氏物語の文学的翻訳であって、講義ではな」く、「原文と対照して読むためのものではない」のであるが、でもそのことは、「原文と懸け離れた自由奔放な意訳がしてあるとか、原作者の主観を無視して私のものにしてしまってあるかのような意味では、決してな」く、「少なくとも、原文にある字句で訳文にそれに該当する部分がない、というようなことはないように、全くないというわけには行かぬが、なるたけそれを避けるようにし」てあるので、「原文と対照して読むのにも役立たなくはないはずであり、この書だけを参考としてでも、随分原文の意味を解くことが出来るようには、訳せていると思う」のであって、その点は前二回の翻訳と同様である。
・・・・
例言
一、この書は独立した一箇の作品として味わってもらうのが本旨であって、なるべく現代人が普通の現代作品に対するように、一字一句の詮索に囚(とら)われずに、安易な気持ちで読んでもらいたいのである。・・・・
一、たとえば本文の中にはしばしば古い詩の文句だの和歌の文句だのの一節を信用したり、またはそういう故人の作に基づいて和歌を詠んだり、洒落(しゃれ)を言ったりしているところがある。それらは、そのもとの詩や和歌を知らないでも、「何か典拠があるんだな」と思いおよびさえすれば、大体何を言おうとしているのか察しがつくはずのことだけれども、・・・・
一、この物語の中で、一番読者が混雑を起しやすく、したがって、一番説明を要するものは、登場人物の呼び方であると思う。現代人が考えると不思議な事であるが、この大長篇の中に出て来る多くの人物のうちで、本当の名前が分っているものは極めて少い。主人公である源氏の君にしてからが、源(みなもと)姓であることは分っているが源の何という人であったか、その正しい名はどこにも挙げていない。・・・・「紫の上」とか、「空蝉(うつせみ)」とか、「夕顔」とかいう名は恐らく物語の世界の渾名(あだな)でさえもなく、作者が便宜上そう読んでいるに過ぎないように察せられる。渾名でも仮の名でも、とにかく名前らしいものがあるのはいいが、大部分の人物にはそういいうものすらも与えられていない。・・・・
一、一度頭注を施した事項でも、読者の便宜を慮(おもんぱか)ってところどころに説明を繰り返してある。
一、和歌は、散文に訳しては講義に堕してしまうし、そうかといって、現代風の和歌に直すことは、私の技倆では覚束(おぼつか)ないし、また専門家を煩(わずら)わしてそういう試みをしたとしても、、恐らくはこの物語の世界の空気とは調和しないものになるであろうから、原作のままを載(の)せる事にした。それで、その和歌の解釈を頭注として書き入れてあるが、・・・・
・・・・
源氏物語の現代語訳の一冊物で、1692ページである。
最初に「序」が4ページあり、次に「例言」として4ページある。
そのあとに、目次が4ページあって、次のページがタイトルで、「谷崎潤一郎訳 源氏物語 全」とあり、タイトルの次のページ(タイトルの裏側)は空白のページで、そのつぎから「桐壷」で始まる本文となる。
「序」には、どのような腹積もりでこの作品を書いたか、が書かれ、次に協力者に対する謝辞がある。
「序」の最後には、本人が亡くなった後にこの一巻本が出版されたために、谷崎夫人による「序文」がある。
文学作品としては、「大層な」構成である。
他の源氏物語の現代語訳をいくつか見たのだが、「前書き」の類はまるでなかった。
まあ、三回目の翻訳であるから、思いもひとしおだったのだろう。
辞書の序文によくみられる「苦労話」は、ここにはまったくない。
ただし、協力者への謝辞があり、これは辞書と同様である。
文学作品に協力者への謝辞が書かれているのも珍しい、と最初に思ったのだが、・・・・
呼んでみると、装丁、挿絵、題字等について、錚々たるメンバーが名を連ねている。
たとえば挿絵については、このように書かれている。
・・・・昭和三十年出版の五巻本以来用いている十四画伯の手になる五十六葉の挿画を、今回も使わしていただく。これは、安田靫彦氏、前田青邨氏以下東西の著名な一流画家が各々(おのおの)四葉ずつ作品を寄せられたもので、現代いかに版を新たにしても、これ以上の源氏絵巻は他に求め得られないからである。
なるほど、このような大家が絡んであるのであれば、一言触れないわけにはいかないのも道理である。
文学作品であれば、通常は、本文のあとに、「解説」があり、作者の経歴だとか、その作品の文学としての評価などが書かれているが、この本では、そのようなものはなく、本文の終わりが記述の終わりである。
その点では、「作者自身が書いた解説」を先頭に置いたようなものといえる。
もっとも、「谷崎源氏」はあまりに有名である。
それについて解説の文章を書ける人は、なかなかいないのかもしれない。
「例言」は、この本の読み方について、作者からの注意事項が書かれている。
これは、私の様な古典文学の初心者には勉強になる。
たとえば、名前についての言及は、とても明快で、古文の教科書に載せたら役に立つ事だろう。
「和歌」の取扱い方は悩むところだろうとの見当はつく。
「散文に訳しては講義に堕してしまう」とは、これはちょっと引っかかる。
「散文に訳する」ことは、「堕落」することなのか。
これは、言い方が悪いのではないかと思う。
その方法は「安易」である、という意味合いだろうか。
その次に、「現代風の和歌に直すことは」、「自分には無理」、「専門家にたのんでも違和感が出るだろう」という。
現代語の和歌に言いかえる、などということが可能なのだろうか。
そういう方法を取っている例はまだ目にしたことがないし、可能だとはとても考えられない。
現代語といっても格調高い文章が続いているところに、現代語の和歌がすんなりおさまるという可能性はまるでないだろう。
パロディーの様に処理するなら手はあるかもしれないが。
この「前書き」については、ここまで書いてきたように、まず内容にひきつけられたのだが、読み進むにつれて、文章の品の良さに心ひかれるようになった。
落ち着きのある文体で、記述が明快だ。
まるで、理科系の論文を読んでいるようである。
ということで、理科系の論文の書き方について見てみる。
木下是雄著
理科系の作文技術
中公新書 624
4 パラグラフ
・・・・
日本の古文にはパラグラフというものはなかった。欧語の文章もそうだったらしいが、多分18世紀ごろまでにパラグラフの概念が確立され、パラグラフごとに改行する記法が行われるようになった。
・・・・教室でパラグラフの意義を教えられた経験のある日本人は数少ないのではないか。
ということなので、この谷崎源氏の序文でパラグラフがどうなっているのかを調べてみた。
単純に、段落ごとの行数を数えるとこうだった。
7, 7, 8, 11, 8, 7
ムラがとても少ない。
内容も、段落ごとにひとつのテーマが書かれていて、まとまっている。
確かに、パラグラフのあり方に合致しているようだ。
谷崎潤一郎が、パラグラフとはどうあるべきか、ということを真剣に考えていたとは想像しにくい。
望ましい文章とはどうあるべきか、という事を考えた末に出てきた「前書き」ではないだろうか。
という事は、普遍的に求められる文章のあり方を谷崎が了解していたということか。
そういえば、谷崎には、「文章読本」という著作がある。
文豪谷崎が書いた"論説文"である。
家の書棚を探すと、丸谷才一と井上ひさしの「文章読本」というべき物があるが、谷崎のものはなかった。
ここまで来ると、読んでみる以外にないだろう(*7)。
家にあったのは以下。
丸谷才一 日本語のために 新潮文庫 昭和五十三年発行
井上ひさし 自家製 文章読本 新潮文庫 昭和六十二年発行
丸谷才一 桜もさよならも日本語 新潮文庫 昭和六十二年発行
大野晋 丸谷才一 日本語で一番大事なもの 中公文庫 一九九〇年発行
最後のものは、1990年発行だが、昭和六十二年に単行本としてまず発行されとの記述が奥付の直前にある。昭和六十二年には随分多くの「文章読本」が出たようだ。
谷崎源氏には古い思い出がある。
高校一年の古文の教科書に、源氏物語の現代語訳を、与謝野晶子訳、谷崎潤一郎訳、そして名前は忘れたが、ある国文学者の訳の三つを並べて、どれがいいか、という設問があった。
国文学にさしたる興味がなかった私としては、与謝野晶子訳はくだけすぎて、また国文学者のものは堅苦しく、谷崎訳が一番いい、と感じたのだった。
おぼろげな記憶では、その時に古文の教師が、どれがいいと思いますか、と生徒に挙手を求めたところ、谷崎訳が圧倒的に多かった。
古典文学にさして興味のない高校一年生だから当てにはならないけれど、まあ、妥当なところと言えるだろう。
39. 新版 眠れない話
新潮文庫
新潮社
広瀬隆
はじめに
・・・・
読者はこのように、あらゆる人間が持つ不完全さ、隠された工場内部の危険な技術、その難解さをおそれて近づこうとせず、自分の意見を吐く勇気もないジャーナリズム、工場体験もない一部の学者、こうしたものが生み出す原子力発電という幻想の世界に身を委(ゆだ)ねてしまっている。ところがその社会は、明日、読者の人生を奪うものである。
私自身は、原子力に関する書物を書きたくない。この暗く陰険な世界に起こっている出来事を、多くの資料を通読してまとめ、分類し、毎日その作業を続け、各地へ旅立って学習会を重ねることが肉体的にひどく辛(つら)い作業であってもそれには耐えられる。しかし腐敗した一部の専門家集団を見ていると、時には空(むな)しさを覚える。それでも本書を書く!
精神的にも肉体的にも苦痛でしかないこの作業を続けさせるのは、私にとっては今も私のふたりの娘のためだけである。娘たちは必ず自分の手で守ってやるつもりである。
・・・・
偶然に二階の書棚でこの本を見付けた。
自分で買うったのだから、見付けた、というのもおかしいが、まったく意識になかった。
東日本大震災で書棚からほとんどの本が落ちた。本の重みで一階の梁(はり)がたわんでいることもあり、思い切って処分することにした。愛着のあるものを残し、体裁のきれいな本は古本として買い取ってもらい、残りは捨てた。
震災後の家中の混乱の中で、どの本がどこにあるのか、あるいはもう家にはないのか、がわからなくなっていた。
あるとき、書棚を見ていて、この書のタイトルと著者名に気づいた。
そういえば以前に読んだことがあったかな、という程度のおぼろげな記憶しかなかった。
奥付を見ると、21年前の刊行である。いつごろ買って読んだのか記憶はない。今の位置で見つかったのは、処分しなかった本のグループに入っていたのだろう。外見はきれいとはいえない。大地震の後、すぐに福島第一原発の悲惨な事故が発生しているから、本の整理をしていたときには、原発は大きな問題になっていたはずである。そのことがあって、この本は捨てられなかったのかもしれない。
「私自身は、原子力に関する書物を書きたくない。この暗く陰険な世界に起こっている出来事を、多くの資料を通読してまとめ、分類し、毎日その作業を続け...」
やはりそうなんだ、といたく共感してしまった。
私は、原発のことが気になって調べだしたのだが、それでようやく少しずつ分ってきた。原子力の世界は、ドロドロと汚れていて、そのなかでいろいろなものがひしめき、うごめいている。それに光を当て、ひとつひとつ取り出して正体を明らかにする、なんてことはとてもいやなことなのだ。私も本当はこんなことにかかわりあいたくはないのだ。
ところがそいつは、毒を持っている。いつそれが吐き出されるのか分らない。どのような毒なのかもよく分らない。ただし、かなり危険なもののようなのだ。ほおっては置けないくらいに。そんなところが我が家の近くにもあったのだ。東海第二原発。自宅から11.4Kmしか離れていないのだった。
福島第一原発では、半径20Km以内は避難措置がとられた。今でも、無断で立ち入ると"処罰"されるところが残っている。すでに、5年間は帰還は無理、と宣言されている所がある。まだ数万の人が自宅を離れて避難生活をしている。
危険です、となぜ言わないのか。安全です、となぜいえるのか。
「・・・・専門家だけを正しいとする社会の誤った風潮がこの犯罪を仕組んできたという認識がなければ、これからの問題は深刻になるばかりである。原発現地の子供たちは、都会的な小ざかしい数字の論争などを待ってはいない。彼らは一刻も早く救いの日がやってくることを待ち望み、それがみたされぬまま、恐怖から逃れるため、次々と愛すべき郷里を離れていっている・・・・」
「都会的」、そうなのだ。都会に住んで、都会から離れたところに建設した原発を議論している。
ああ、確かに、都会に原発を作るという愚を犯なかった点で彼らはよく分っていた。原発は事故がおきると大変だから、都会には作ってはいけない。都会につくるとしたら、安全確保にとんでもない費用がかかる。分っていたんだね。彼らは。
「小ざかしい」とは言い得ている。ただし、私は「サル知恵」と言っている。人間の想像力なんてたかが知れている。自然は人間の予想を簡単に裏切る。だが、専門家、あるいは学者たちは、分ったことにしないと生きてはいけない。
安全対策が十分なものかどうかは分らない。学者というものは、絶対的なレベルは取り上げない。学者が出来ることは、今までのレベルを少し前進させる、というだけなのだ。この相対的な進歩だけが専門家のできることだ。
市民が絶対的な評価をする。しなければいけない。自分と家族の生活がかかっているのだ。評価の結果に責任を持つのも自分である。すべて分っているのではないことは承知している。だが、進むにしても、止まるにしても、退くにしても、自分で決めて実行し、自分で結果の責任を取る。
福島第一原発の津波は最大で5mとされていたが、実際は15mの津波が来た。その結果どうなったか。「予想値より10m高くなる可能性がある、と考えれは良いのだ」という人がいるのだ。あきれた、というのはこのことだろう。「専門家の言うことはまるで当てにならなかった」、ということではないのか。
専門家の選び方がまずかったのだろうか。決してそうではない。期待に応えられる専門家というものがそもそもいないのである。
この「はじめに」には、チェルノブイリ事故が引き合いに出されている。その時点で最悪の、そしてダントツの大原発事故だった。
「・・・・四年前には最も過激な言葉に聞こえたであろう筆者の"チェルノブイリ事故の惨状予測"は、今となっては現実の何分の一にも達しない過小評価であったことが、ソ連の悲しむべき子供たちの死によって実証されつつある。美浜で起こった事故は、われわれが寸秒を争う危険な状況に置かれていることを教えながら、またしてもその事実はほとんど伝えられていない。」
この書の次の版がでるとしたら、福島第一原発の惨状についてページを費やすことになるだろう。そして「眠れない話」は、「目が覚めたあとの話」と変える必要があるかもしれない。「大事故が起こるかもしれない、起きたらどうしよう」という"眠れない"時期は過ぎて、「大事故が起きてしまった、これからどうしよう」と立場が変わった。いまこそ、起きて、立ち上がるときだろう。
40. 全訳 漢辞海
三省堂 2002年
戸川芳郎監修 佐藤進・濱口富士雄編
監修者のことば
・・・・
さて、漢字の辞典『漢辞海』は、いまここに公刊の時を告げる。
(中略)
・・・・ここでは一旦、日本語表記の漢字から離れて、迂遠ではあるが原来の漢字によって表記された漢語[hànyŭ](Chinese language)にたちもどることを企図したのである。(筆者注:[ ]の中の文字は「漢語」のふりがなの位置に表記されている)
(中略)
漢字を単に和訓に置き換えるのではなく、漢語(Chinese word)として捉え、的確な例文から、実際の文脈にそって語義を読解する。(以下略)
前書き・後書きには特に注目しているのだから、この辞書を入手したときには、この文章は当然、気をつけて読んだ はずである。しかし、特に感じるところがなく、この前書き・後書きのコーナーに取り上げようとは思わなかった。
もともと、この辞書を入手した理由は、それぞれの漢字ごとに篆書体が掲載されていたからである。
本サイトの「最近の写真」のコーナーに茨城県常陸太田市の佐竹寺を取り上げており、その中で 「重修碑」という石碑の文章を解読しようとこころみているところがある。 石碑の上部には篆額(てんがく)という、題名の様なものが篆書体で書かれた部分があり、 それをどう読むかを、辞書の篆書体と比較して確認しようとしたのである。
そのために、「重修碑」の3文字について辞書の篆書体の部分をこのホームページに転載したい。
篆書体の文字はパソコンで文字コードで表示させることはできないので、辞書から画像としてコピーする必要があるが、著作権上、引用として許される範囲ではない。
発行元の三省堂に問い合わせても、このような個人的な問い合わせにいちいち回答をしてはくれないだろうな、などと考えているうちに、日が過ぎてしまった。
いつまでもほおってはおけないので、一応三省堂に問い合わせて、回答が来ないか、だめという回答が来た時にはあきらめようと決め、問い合わせのメールを送った。
毎日メールをチェックしていたが、回答は届かず、やはりだめか、とあきらめかけていたころ、メール送信からちょうど1週間後に、ついに回答が届いて、原典を明記すればOKであり、 ネットにアップしたときにはURLを連絡してください、ということも書いてあった。メールの文面では、3文字くらいならいいだろう、というニュアンスのようだ。
さっそくお礼のメールを送信して、編集を開始した。
3文字分の篆書体の部分をスキャナー機能のある複合機でスキャンし、篆書体の部分だけを切り出し、3文字分をつないだ画像にするという作業だった。
使用した複合機からのスキャンは、読み込むサイズが最小でA5と大きすぎるので、大きさを自分で指定する必要があった。ページの端から何センチという指定なので、余裕をみて縦・横ともに10cmとしてスキャンし、必要な篆書体の部分を画像処理ソフトで切り出すのだが、切り出し作業では、篆書体の部分だけでなく、 その周囲も自然に目に入る。
その時に、「修」の文字のところに、「重修」の文字があるのに気付いた。例文として、「乃重修岳陽楼」とあり、訳文として「そこで岳陽楼をもう一度建てた」とある。岳陽楼という建物の名前がでてきて、これは佐竹寺の件とよく合う。そこで、語義の欄を注意して読んでみた。「修」には、修飾する、(建物を)建てる、修理する、などの語義がのべられていた。
「修」に「建物を建てる」という意味があるというのだ。それなら、佐竹寺の場合も、「もう一度建てた」という意味なのかもしれない。「重修」については「重ねての修理」といままでは理解していたが、修正が必要かもしれない。
しかし、「修」に「建物を建てる」という意味があるのだろうか、と思い、もう1冊の漢和辞典に当たると、見つからない。これは詳しく調べる必要がある。翌日、図書館に調べに行くことにする。諸橋の大漢和辞典、白川の字通、そのほかの漢和辞典、それと中国では「建てる」という意味があるのかもしれない、ということから中日辞典もチェックが必要だ。
翌日、市の図書館に出かけた。諸橋、白川のどちらにも、「建てる」という語義は見つからなかった。そのほかの辞書を何冊かあたったが、「建てる」と書いたものはい。
一つだけ、熟語として「重修」を載せているものが見つかった。大修館書店の大漢語林で、意味として重ねて編集する、重ねて修理する、修繕する、とあり、例文として、文章自体は省略されているが、「岳陽楼記」とあるのは、漢辞海と同じ文章を指しているに違いない。ここでも修理、修繕ということである。
中日辞典はどうか。大型本、小型本など3種類を見たが、どれにも「建築する、建設する」という意味をのせていた。例文を見ると、建物だけでなく、道路をつくる、橋をかける、というときにも使うようだ。やはり中国では「建てる」という意味がある。小型の辞書にも載っているから一般的に使われているのだろう。
ということは、中日辞典にある語義に一番近い物が漢辞海だったのである。
そこで、改めて漢辞海の前書きにあたる「監修者のことば」を読みかえしてみた。
「日本語表記の漢字から離れて、迂遠ではあるが原来の漢字に依って表記された漢語」とか、「漢字を単に和訓に置き換えるのではなく、漢語(chinese word)として捉え、的確な例文から、実際の文脈にそって語義を読解する」という表現が、今度はしみじみと理解できた。
なるほど、この「監修者のことば」には、編集の意図がきちんと書かれており、それはとても重要な内容だった。しかし私は最初に読んだときにそれをくみ取ることができなかった。
あらためて、「前書き」の重要さ、そして面白さに気付いた瞬間だった。正直なところ、とてもうれしかった。
ここまでの私の文章で、私が受けた感動をどれだけ表現できているだろうかと考えると、はなはだ心もとないが、書かずにはいられず、くどくどと書いてしまったという感がある。
しかし、私にとっては前書きの重要さ、面白さの「再発見」だったのは確かである。
「重修」を「建て直す」と表現することが妥当であるということの検討は、上記でも触れた佐竹寺の記事にくわしく書いたので、参考にされたい(リンク先のコメント欄の(11)にある)。
【追記 2019/11/9】
"修"が"建てる"という意味を含むか、について、他の例が一つ見つかった。
秋本吉徳 常陸国風土記 講談社学術文庫 講談社 2004年12月 第4刷
そのなかの「十五 香島郡(二)」(同書 p.116)に、「神の宮を造らしめき。爾(それ)より已来、修理ること絶えず」とある。"修理る"はルビにより"つくる"とされており、その後の注に次のような詳しい説明がある(同書 p.120)。
掘立柱の建造物では、柱自体が駄目になるので、"修理"と言うよりは"建て替え"の方がふさわしいと感じられる。もっとも、岳陽楼が掘立柱の建造物なのかどうかについては、全く分らない。しかし、"修理る"とかいて"つくる"と読ませるのだから、すくなくとも当時は"修理"とは"建てること"を含んでいたことになる。したがって、"重修"が"ふたたび建てる"、"建て直す"という意味を持つことは妥当性がある。
(*1)、(*2)は、2011/10/21にネット上で確認した。
(*3)コンサイス世界年表 三省堂編集所編 三省堂(昭和51年)
(*4)精講日本史 永原慶二編 学生社(1970年)
(*5)日本の詩歌 10 高村光太郎 中央公論社 中公文庫(昭和49年)
(*6)は、2012/6/21にネット上で確認した。
(*7)さっそく読んでみた。「小品いろいろ」の(2)でその感想を書いた。